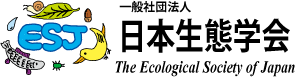(仮称)苫東厚真風力発電事業計画の評価再調査・事業変更を求める要望書
(仮称)苫東厚真風力発電事業計画地には自然度の高い湿原、草原、湖沼等がまとまって存在し、多数の希少動植物が生息・生育しており、風力発電所の建設と運用による環境改変が当該地域の生態系や生物多様性に多大な影響を及ぼすことが予測されている。そのため、2020年には環境影響評価配慮書に対し日本生態学会北海道地区会から「苫東厚真風力発電事業計画段階環境配慮書に対する意見書」を、2022年には環境影響評価方法書に対し日本生態学会から「苫東厚真風力発電事業計画の事業区域の変更を求める要望書」を事業者他に提出した。また、日本鳥学会から「(仮称)苫東厚真風力発電事業に関する意見書」を、2021年には日本鳥学会から「(仮称)苫東厚真風力発電事業に対する事業中止要望書」を事業者他に提出した。しかしながら、当事業では、これらの意見は全く反映されず、現在、環境影響評価準備書(以下、準備書)の審査が進められている。特に、準備書では、再三の要望にもかかわらず、当事業による環境改変が生態系や生物多様性に与える影響を予測するために必要な調査が多くの項目で実施されておらず、また、実施された項目であってもその質・量に乏しいことから、科学的判断を示すことが困難な状況である。したがって、本事業の影響に関する再調査を実施し、その結果が明らかとなるまでは本地域における事業を停止すること、再調査の結果をもとに計画を見直すこと、環境影響の回避・低減が不可能である場合には事業地を変更することを改めて要望する。
1) 事業地の生態学的重要性
事業地には自然度の高い湿原、草原、湖沼等が存在し、これらが景観単位として機能しており、特に以下の点で重要である。
- 事業地面積は、環境省「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」に選定された安平川湿原に匹敵する460 haに達する(文献1, 2をもとに計算)。
- 事業地は、大部分が海浜を含めた湿原・草原で占められている。事業地に含まれる浜厚真海岸は、「北海道自然環境保全指針」において「身近な自然地域」に選定されており3、各種公共事業や開発等の計画や実施の際に、適切に保全への配慮を行うことが求められている。
- 事業地は、ラムサール条約登録湿地であるウトナイ湖に隣接するとともに、日本野鳥の会・バードライフインターナショナルによる重要野鳥生息地(IBA)およびコンサベーションインターナショナルによる生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)に囲まれており、これらと一体となることで動植物の重要な生息生育地となっている。
- 事業地は勇払原野の中でも有数の希少種・絶滅危惧種の生息生育地であり、鳥類では文化財保護法指定種(天然記念物・特別天然記念物)に5種、国内希少野生動植物種指定種に9種、環境省レッドリスト(環RL)に41種、北海道レッドリスト(道RL)に46種が確認されている4-7。魚類では環RLおよび道RLにそれぞれ3種5, 7, 8、節足動物では環RLに18種、道RLに7種が6, 7, 9、維管束植物では環RLに9種、道RLに5種が確認されている6, 7, 10。
- 鳥類では、チュウヒ(環RL絶滅危惧IB類・国内希少野生動植物種)、オジロワシ(環RL絶滅危惧II類・国内希少野生動植物種)、およびタンチョウ(環RL絶滅危惧II類・国内希少野生動植物種・特別天然記念物)の重要な生息・繁殖地である1, 5, 11, 12。特に、チュウヒに関しては、事業地はサロベツ原野に次ぐ国内2番目の繁殖地となっている。
- 植物では、ナガバエビモ(環RL絶滅危惧IA類・国内希少野生動植物種)をはじめとする海浜や池塘等の特殊な生育地に現れる水草の絶滅危惧種が確認されており6, 7, 10、事業地内は、各地でほぼ消失した海浜草原・湿原が自然状態に近い状態で現存する希少地域である。
2) 準備書における環境影響評価の問題点
事業地は希少動植物の重要な生息・生育地であるが、準備書ではこれらの生息・生育地の内部または近接するエリアの自然度の高い植生帯に風車を建設する計画となっており(図1)、事業者の環境影響評価は、調査解析方法に問題があることで科学的根拠が希薄な推測に基づくものとなっている。したがって、生態系・希少動植物への事業の影響を回避または低減可能と結論することは不可能である。以下に、これらの指摘内容を具体的に述べる。
- [準備書全体] 現地調査データの質・量および解析の信頼性が乏しく、科学的な解釈に問題点が多い。チュウヒやアカモズでは営巣地の見落としが複数あり(アフターケア委員会の調査に基づく)、バードストライクの確率が高いチュウヒの幼鳥のデータを取得できていない。渡り鳥・ガン類の衝突確率の推定では、不適切なデータの使用が見られる(参考資料1:北海道新聞2024年10月16日第3社会面)。さらに、専門家複数名の意見を準備書に掲載しないといった、環境影響評価として不適切な手続きが行われている(道環境影響評価審議会準備書2次質問で指摘・事業者認知)。上記のことより、再調査の必要性が各所に認められる。
- [チュウヒ] 事業地およびその周辺にチュウヒの営巣地が複数箇所存在しているにもかかわらず、「風力発電事業におけるクマタカ・チュウヒに関する環境影響評価の基本的考え方」(以下、「基本的考え方」)13や「チュウヒ保護の進め方」14、専門家の意見および論文等の知見を参考とせず、風車配置が検討されている。事業者は、「基本的考え方」において、既存風車の近くに営巣したチュウヒの巣とその風車との最短距離を基にそれより遠ければ影響が小さいとしているが、「基本的考え方」では、そのことで影響が低減・回避されるということは記述されていない。既に存在するチュウヒ営巣地の近くに風車を建設した際の影響を、風車が既にある状態で営巣したチュウヒと風車の離隔距離と同じと仮定して予測することは、科学的に不適切な分析方法である。これは「基本的考え方」にある「営巣地と連続する草地や営巣中心域、隣接ペアの干渉行動が生じる場所に風車を建設すべきではない」という指針とは相容れない。もっとも重要な点の一つとして、計画された風車位置は全てチュウヒの主要行動圏内にあり、さらに本事業地では、これまでに風車からの離隔距離が150 mの所に1巣、180 mの所に1巣が確認されているものの、事業者の調査では見落とされている(アフターケア委員会調査に基づく)。また、これらの離隔距離は、「基本的考え方」における150-200 mの範囲にあり、巣への影響を避けるには、さらなる離隔距離が必要である。加えて、離隔距離は1.2 kmでも不十分という研究もある15。以上のように、複数の風車がチュウヒの巣との離隔が不十分であり、現行の配置計画では、風車建設の影響は低減もしくは回避できないと判断せざるをえない。チュウヒに限らず、バードストライクは離隔距離が十分でない場合に、飛躍的に危険性が増す。さらに、チュウヒは準備書に掲載された専門家の試算において、事業にともなう生息地改変によりつがい数や巣立ち雛数が無視できない程度に減少すると予測されているが、これに対する保全措置は準備書には記載されていない。
- [タンチョウ]風車との離隔が約400 mといった、離隔距離が必ずしも十分とはいえないタンチョウ営巣地が事業地内で確認されている。これまで、風力発電事業地内でタンチョウの営巣事例は報告されておらず、タンチョウに対する風車建設の影響評価は慎重に行う必要がある。加えて、現在、北海道に生息するタンチョウは個体数を回復させつつある状況にあり、事業地内の営巣地および周辺は将来的に分布拡大の拠点地域となる可能性が高いため、風車の建設を控えるべきである。
- [バードストライク] バードストライクの予測値は、いずれの種においても押しなべて高い。年間予測衝突数が、令和3年のオジロワシにおいて0.139(環境省モデル)と0.319(由井モデル)、令和3年のガン類で1.775(環境省モデル)と4.702(由井モデル)となっており、道内の他事業でこれまで問題となった高い推定値と比較しても突出して高いが、これに対する保全措置が準備書に記載されていない。加えて、各種の飛翔高度の測定は正確さを欠いており、影響予測値は低く推定されている。年度により渡り鳥の調査時期および調査期間が異なり、令和3年の予測値が最も精度が高い一方、令和4年と令和5年の予測値は猛禽類調査等に付随して得られた定量性のないデータに基づいて算出されている。夜間の渡り鳥の衝突確率の評価は、データが全く取得できておらず、不十分である。例えば、ガン類の高い予測衝突数に対して、夜の渡りに対しライトを点灯させることで回避を促すとしているが、その効果はこれまで証明されていない16。
- [植生]本海浜区域の植生と景観の特徴は、日本に残された数少ない海浜性の植生ゾーネーションが残っていることにある。しかし、本計画では、海浜の一植生帯に風車が建設され、特定の植生帯が大きく消失することになる。本計画書の風車配置では、特定の植生帯が大きく減少するため、独特の植生ゾーネーションをなす海浜景観の保全は不可能であり、事業と景観保全の両立を図ることはできない。加えて、自然植生度10の海浜植生を大規模に改変することとなるが、これらへの影響および評価についても科学的根拠に基づく言及はない。
- [植物]重要な植物種としてリスト(表3.1-44)されたもののうち、建設計画地を含む海岸植生帯において、キタノコギリソウ(ホロマンノコギリソウ)やシコタンキンポウゲの定着がアフターケア委員会の調査により確認されている(北海道大学総合博物館陸上植物標本庫(SAPS))。なお、近接する湿地においても複数の重要種が確認され、浜厚真海岸からモウコムカシヨモギが50年ぶりに再記録された17。準備書においては、上記植物種の記載がないことを始めとして、植物相の把握が不十分である。さらに、重要な植物種の生育場所が複数見落とされており、これらに対する影響が評価されていない。植生についても、準備書では、未調査の植生が複数認められ、データの信頼性は極めて低い。少なくとも、海岸線に沿った区域に連続した風車の配置は避けるべきであり、再調査と再解析を行った上で、配置の見直しが必要である。
以上のように、当事業に対する環境影響評価は科学的信頼性を著しく欠き、事業実施による環境改変が生態系や生物多様性に与える影響を回避・低減できる科学的根拠は全く示されていない。むしろ、当事業が実施されれば、事業地内外の生態系に大きな影響が及び、その結果生物多様性が低下することが十分に予見される。このような場合には、風力発電事業と環境保全の両立は困難であり、計画は見送られるべきである。
日本生態学会と日本鳥学会は、科学的評価を行うには現行の環境影響評価準備書では不十分であると判断し、再調査の実施を強く要望する。さらに、再調査期間中の工事停止を求め、再調査の結果、環境影響の回避・低減が不可避と判断される場合には、事業地の変更を求める。これらの措置が取られない限り、当該風力発電事業が生態系に重大な影響をもたらす危険があることを強く懸念する。
引用文献
- Senzaki, M., & Yamaura, Y. (2016) Surrogate species versus landscape metric: does presence of a raptor species explain diversity of multiple taxa more than patch area? Wetlands ecology and management, 24, 427-441.
- Kitazawa, M., Yamaura, Y., Senzaki, M., Kawamura, K., Hanioka, M., & Nakamura, F. (2019) An evaluation of five agricultural habitat types for openland birds: abandoned farmland can have comparative values to undisturbed wetland. Ornithological Science 18, 3-16
- 北海道環境生活部環境局自然環境課. 北海道自然環境保全指針. (2025-1-08参照)
- 先崎理之,松井晋,江崎逸郎,大畑孝二,中村聡 (2021) 浜厚真の鳥類~浜厚真Bioblitz2021報告~.石狩川流域湿地・水辺・海岸ネットワーク. (2025-1-08参照)
- 日本野鳥の会. 勇払原野保全構想に係る対象範囲南部・重要鳥類生息データベース.(2020-06-10問い合わせ・参照)
- 環境生活部環境局生物多様性保全課 (2019) 北海道レッドリスト【北海道】. (2025-1-08参照).
- 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 (2020) 環境省レッドリスト2020. (2025-1-08参照)
- 北海道ラムサールネットワーク 浜厚真Bioblitz2021魚類データベース.(2021-12-05問い合わせ・参照).
- 浜厚真Bioblitz2021 昆虫班(2021)浜厚真の節足動物~浜厚真Bioblitz2021報告~.石狩川流域湿地・水辺・海岸ネットワーク. (2025-1-08参照)
- 浜厚真Bioblitz2021 植物班(2021)浜厚真の維管束植物~浜厚真Bioblitz2021報告~.石狩川流域湿地・水辺・海岸ネットワーク. (2025-1-08参照)
- Senzaki, M., Yamaura, Y., & Nakamura, F. (2015) The usefulness of top predators as biodiversity surrogates indicated by the relationship between the reproductive outputs of raptors and other bird species. Biological Conservation 191 460-468
- Senzaki, M., Yamaura, Y., & Nakamura, F. (2017) Predicting off-site impacts on breeding success of the marsh harrier. Journal of Wildlife Management 81, 973-981
- 環境省 (2024)風力発電事業におけるクマタカ・チュウヒに関する環境影響評価の基本的考え方. (2025-1-08参照)
- 環境省自然環境局野生生物課 (2016)チュウヒ保護の進め方. (2025-1-08参照)
- 浦達也,長谷部真,平井千晶,北村亘,葉山政治 (2019) 繁殖期のチュウヒが風力発電施設の建設により受ける影響とその行動.自然保護助成基金助成成果報告書 vol. 28,50-57
- Rebke, M., Dierschke, V., Weiner, C. N., Aumüller, R., Hill, K., & Hill, R. (2019) Attraction of nocturnally migrating birds to artificial light: The influence of colour, intensity and blinking mode under different cloud cover conditions. Biological Conservation 233, 220-227
- Shutoh, K., Michikawa, F., Igarashi, H., & Tsuyuzaki, S. (2025) Re-recognition of potentially introduced Symphyotrichum ciliatum (Ledebour) G. L. Nesom (Asteraceae) in Japan with notes for taxonomic confusion on typification of the species. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (in press)
以上