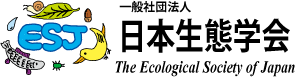第4回(2011年) 日本生態学会大島賞受賞者
大塚俊之(岐阜大学流域圏科学研究センター)
大手信人(東京大学大学院農学生命科学研究科)
西廣淳(東京大学大学院農学生命科学研究科)
野田隆史(北海道大学地球環境科学研究科)
選考概要
大塚俊之氏は,森林構造の遷移的変化に伴う炭素循環の長期変化について関心をもち,1998年からは現在勤務している岐阜大学の高山試験地において研究を行っている。高山試験地における炭素循環研究の特徴は,微気象学的なタワーフラックス観測という新しい測定手法と,古典的な積み上げ式の生態学的手法という二つの独立した手法によって生態系純生産量(NEP)の精密な測定を行っていることである。このなかで大塚氏は、生態学的手法によるNEP測定手法を更新し,樹木の成長,枯死量を継続的に測定することによって微気象学的手法の時間スケールと比較可能な純生産量(NPP)推定手法を確立した。そして,森林遷移にともなって炭素は生態系のバイオマスに蓄積するのではなく,枯死木や土壌有機物などのネクロマスに蓄積していくことを示した。さらに,8年間の継続計測の結果,生態学的手法によって測定されたNPPは微気象学的な手法によって求められたNEPとパラレルに変動している一方で,ネクロマスの分解呼吸量は年によらずほぼ一定であることを示し,分解呼吸量ではなく生産量がNEPの年々変動に寄与していることを実証した。これらの成果は,Agricultural and Forest Meteorology,Ecosystems, Global Change Biologyなどの一流の国際誌に掲載されている。こうした森林生態系の炭素循環における新視点は,大塚氏の10年間に及ぶ多項目の継続観測により達成されたものであり,今後も大きな成果を上げるものと期待される。以上の理由により、大塚氏を日本生態学会大島賞の授賞者として推薦した。
大手信人氏は、滋賀県桐生試験地の源頭域を中心とした森林河川の集水域において、長期にわたる丹念な現地調査の積み重ねにより、窒素循環や窒素の流出過程を水文過程との関連から明らかにした。また、それらの結果を、アジア・モンスーン気候下の特徴的な現象として概念化した。これらの成果は、従来、北米や西欧における研究結果に基づいて組み立てられてきた森林生態系の窒素循環の概念枠組みの再検討の必要性を示唆するものであり、我が国発のオリジナリティーの高い業績として評価できる。また、大手氏は、各種の安定同位体比を用いた水・物質循環解析の手法を駆使した先駆的な研究も推進している。例えば、琵琶湖の流入河川において、河川水中の硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比の季節的・地理的な変動を詳細に調査し、その結果から、河川に対する下水および大気由来の窒素負荷の相対的な寄与を推定することに成功している。以上の研究以外にも、森林からの炭素の流失、乾燥地の植物の水利用、病害が森林物質循環に及ぼす影響、といった幅広い分野で顕著な業績があり、そのいずれもが地道な現地調査によるものである。研究成果は、Ecological Applications, Water Resources Research, Global Biogeochemical Cycles などに掲載され、国際的にも高く評価されている。さらに大手氏は、日本生態学会大規模長期生態学専門委員会や日本長期生態学研究ネットワーク(JaLTER)の活動にも積極的に関与しており、我が国における長期生態学研究の推進にも大きく貢献している。以上のことから、大手氏は生態学会大島賞の候補者として相応しいと判断した。
西廣淳氏は、日本の保全生態学をけん引する若手・中堅のリーダー的存在である。初期は、サクラソウやタデを対象に、異型花柱性の進化生態学的研究を行った。しかし、大島賞候補者としての西廣氏の顕著な業績は、その後の霞ケ浦における水生植物の復元に関する保全生態学的研究にある。湖沼の管理にともなう水位変動の喪失が、多くの水生植物の個体群を衰退させていることを、長期データや野外実験などにより明らかにした。さらに、土壌シードバンクを活用した絶滅危惧植物の復元の研究は、湖岸植生の再生手法の確立に大きく貢献している。生態系の保全や再生は、現場の感のような必ずしも科学的とはいえない根拠に基づいて行われることが少なくないが、西廣氏による一連の研究と実践は、仮説検証手続きを経て順応的に再生を行なう確固たる道筋を示した我が国では数少ない事例である。西廣氏の論文数や論文の被引用回数は、他の候補者と比べて格段に高いわけではないが、学会やシンポジウム、セミナーなどにおける依頼講演は、同年代の生態学者のなかでは、抜群に多いことが特徴として挙げられる。西廣氏の地道な研究成果が、行政や市民などに対してインパクトの高いものであることを物語っている。以上、西廣氏は日本生態学会大島賞の受賞者としての資格を満たしていると判断した。
野田隆史氏は、岩礁潮間帯の群集生態学・個体群生態学を専門としてきた。研究テーマは、1)巻貝キサゴの生活史戦略と個体群動態、2)チシマフジツボの幼生加入量の時空間変動、3)階層的空間スケールにおける個体群や種多様性の時空間変異、に大別される。これまでに発表された31報の英文論文のうち、もっとも顕著な業績として認められるのは、2004年のPopulation Ecologyに掲載された総説である。ここでは、空間スケールの階層間で見られる群集パターンのコンテクスト依存性と予測可能性の差異について論じるとともに、種の共存をはじめとする群集生態学のさまざまなメカニズムは、複数の空間スケールの生態パターンの同時把握によって解明できるという新たな研究指針を提供した。この見解に基づき、野田氏は独自のプロジェクトを立ち上げ、日本列島の太平洋側の6地域の海岸を対象に長期データを蓄積し、研究を進めている。その成果の一端は、動物生態学のleading journalのひとつであるJournal of Animal Ecology等に掲載され、今後も成果発表が続くものと期待される。さらに日本語による啓蒙書も執筆し、代表作としては「メタ群集の共存メカニズム」(シリーズ群集生態学「メタ群集と空間スケール」(2008)に収録)がある。このように海洋性動物を中心とする個体群・群集生態学に空間横断的アプローチを採用し、長期野外調査を推進している氏の研究は、大島賞に値すると判断した。
今回、4名の大島賞候補者の推薦に至った。細則には「授賞は毎年原則として2名」とあるため、4名の推薦に至った経緯を以下に説明する。まず、4名はいずれも、「例えば野外における生態学的データの収集を長期間継続しておこうことなどにより生態学の発展に寄与している」という細則の条件を十分満たしていることが挙げられる。いずれの候補者も、昨年であれば受賞に至った可能性が高いという意見もあった。つぎに、従来の大島賞のイメージは、同じ場所で生態観測を長期間行ってきた研究に限定されているイメージが強く、生態学会内における潜在的な候補者の母集団が、特定の分野に限定されてきた感がある。大手氏と大塚氏の研究は、このイメージに合致したものであるが、今後、野田氏のような空間横断的研究や、西廣氏のような科学的な順応的管理の実践研究も、授賞対象として積極的に奨励すべきではないかという意見である。これは、昨年の委員会で課題として提出された、大島賞の新たなイメージ形成とも合致する。最後に、一度に4名の受賞は、毎年原則2名の縛りを大きく超えていると見ることもできるが、昨年は受賞者ゼロ、一昨年1名、であったことを勘案すれば、2年間で4名、あるいは3年間で5名であり、必ずしも過剰とはいえないことも理由として挙げられる。
選考委員会メンバー:辻和希,津田みどり,永田 俊,井鷺 裕司,久米 篤,宮下 直(委員長),宮竹貴久,谷内茂雄,吉田丈人