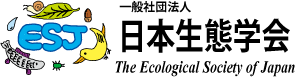会長からのメッセージ -その6-
1/fと生態系の保全
前回の「会長メッセージ」から少し間があいてしまいました。先にお知らせしたように、いよいよWileyからEcological Research*1 が発刊されました。それについては、またいずれ機会を設けてお話したいと思います。
今回は、最近感じたことをお話させてください。
生態学会の会長を努めていながら、他学会のことを話すのは恐縮ですが、私はOikos誌の編集委員を10年ほど努めています。私がOikos誌から編集委員の打診を受けてすぐに飛びついたのは、1990年代にJohn H. Lawtonさんがシリーズで執筆されたView From the Parkというエッセイに惹かれた経験があったからです。そのエッセイ、都立大学(現首都大)や京都大学生態学研究センターの図書室で、発刊されたらすぐにリアルタイムで読んでいました(当時はインターネットで読むことなんか出来なかった)。若い研究者としてどうあるべきか、生態学に一般論はあるか、研究テーマはどう設定すべきか、年寄り研究者はどうあるべきか、等々、刺激のある問いかけの中で自身の考えをそれとなく挟み込む。その文章に、相槌をうったり、考えを改めたり。不思議なことに、考えが合わなかったとしても、その文からは不満も敵意も抱きませんでした。やや難解なイギリス英語で、節々に出てくる冗談や言い回しは全くわからないものの、ああこうやって啓蒙や物事は進めていくのだと、感心した覚えがあります。Lawtonさんは、京都大学生態学研究センターがその設立時に手本の一つにしたイギリスSilwood ParkにあるImperial College、Center for Population Ecologyの所長を長く務められ、その後英国NERC(自然環境研究会議)などで科学行政や環境行政に携わった方です。日本からもSilwood Parkを訪ねたり留学したりした研究者も少なからずいるでしょう。
私は、最近までLawtonさんのエッセイに刺激を受けたこと、すっかり忘れていました。ところが昨年、Oikos誌編集長が、Lawtonさんに20年ぶりのエッセイを執筆していただくことに「成功」しました*2。「以前、こんなエッセイを書いたことはすっかり忘れていたし、こんな偉そうなことを私が書いたなんて信じられない」、といったようなことから始まるエッセイです。その中で、エッセイのなかでもっとも論争となったのは、20回目の「The science and non-science of conservation biology」*3だと振り返っていました。読んだ記憶はありますが、内容はすっかり忘れていました。そこで、(今回は図書室へ行かず)ネットから該当部分のpdfをDLして早速読み返してみました。そうだ、1/f だった! 物事の考え方は、何かの刺激が根となり、それが幹や枝となっていつのまにか成長して行きます。このLawtonさんのエッセイ、生態学者は社会にどうあるべきかを私が考える時、その根になっていたことに思い当たりました。
かいつまんで言えば、保全に対して生態学者は 1/f を肝に銘じろ、ということです。どんな個体群でも生物群集でも、時間とともに変動していくことは生態学を少し学んだ方なら良く知っているはずです。撹乱による影響も然り。小さい撹乱は頻繁に起こるし、稀には壊滅的な大規模な撹乱も起こります。撹乱の規模が f だとすれば、その頻度は、Lawtonさんによれば、1/f ということになります。自然のノイズは(それがなんであっても)短期的には小さい擾乱として頻繁に作用し、長期的には魔物のように生態系に襲いかかり、種を絶滅させ、生物群集をガラリと変化させます。であれば、種であろうが生息場所であろうが、どのような状態を保全するかという命題は、生態学者なら生態学の課題として相応しくないことはすぐに理解出来るでしょう。人間が感じる自然の望ましい姿は生態学の理論ではなく、社会や倫理(道徳)、心理、美学、文化や宗教など、さまざまな要因によって決まるものです。Lawtonさんは指摘します、一般の人は驚くかも知れないが(そして生態学者はがっかりするかも知れないが)、生態学は望ましい自然の姿についてゴールを設定する学問ではない、と。自然界の 1/f を考えれば、そんなゴールはないというのが生態学の理論の帰結でしょう。実際、社会のゴールは政治や社会や人それぞれの生き方や価値観が設定する問題です。しかし、彼の主張の結末は、ここでは触れないでおくことにします。
そんなLawtonさんの主張を読むと、種や生息場所の保全をどうするか、生態学者ならだれでも深く洞察したくなるものです。私もそうやって、折々揺れながら考えて来ました。自分スケールの1/f時間(人生)だけ(お気に入りの種や生息場所が)保全(保護)されればいいのだ、では、あまりにも傲慢ではないか。自然の「摂理」なら良いが人が破壊するのはダメだというのは、もしかしたら、ある種の宗教観ではないか。生態系の保全という考えに科学的基盤がないなら、科学的でないという批判は最大の褒め言葉になりはしないか。生態学はゴールを決める学問ではないかも知れないが、少なくとも決定する前に、そのゴールの意味を生態学の知見を駆使して先験的に説明することは出来るのではないか。もし、ある種や生息場所について望ましいゴールを社会が(そして私達もその一部であるが)設定したとすれば、そのゴールに到達すべき方法や条件などに生態学は沢山貢献出来るはずではないか、等々。そして次のような「比較的安全」な結論に至ります。もしどこかに堤防を設置とするとなれば、経済的で強靭で壊れにくい[そして自然に配慮した]堤防をいかに造るか、その研究を行うのは土木研究者でしょう。しかし、その地域の堤防設置を決めるのは、土木学ではないはずだ。であるなら、生態学だけが生態系の保全について正義感に満ちたゴールを決められるかのような幻想は捨てるべきでしょう。望ましい自然や環境について社会のゴールを決めるのは、多様な考えをもつ社会の構成員であって、けっして生態学ではないのだから。
学会は多様な会員から構成されています。年齢も、性別も、社会的立場も、思想信条も異なります。同じ生物好きでも、自然教条主義的な方もいれば人間本意主義的な方もいるでしょう。Brahmsが好きな人もいれば、Metallicaが好きな人もいるはずですから(私の書棚にはBudgieのLPが全部ある!)。人それぞれ、考え方も興味も異なることが学会の強みです。学会は権威でなく、学問的価値の最大公約数を集約する場でもありません。ワクワクするような研究成果を聴き、発表し、多様な研究者が真摯に議論することで未来に向かって地平を前進させる。これこそ会員であることの最大のメリットです。この多様性を意識せず、もしある種の成果や学会が権威であるかのような社会的働きかけをしたら、また、特定の領域や考え方だけを標榜するようなことがあれば、それはもはや学会ではないでしょう。一方で、生態学の課題を探求しながら、私達の社会をより良くするためにその成果を活かすことは常に考えるべきでしょう。しかしそれは、学会なんかではなく、学会を構成する多様な会員の個々の活躍にかかっていると思うのです。
2019年2月20日 会長 占部城太郎
- *1 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401703
- *2 Oikos 127(9): 1231–1232, 2018. doi: 10.1111/oik.05765
- *3 Oikos 79(1): 3-5 , 1997.